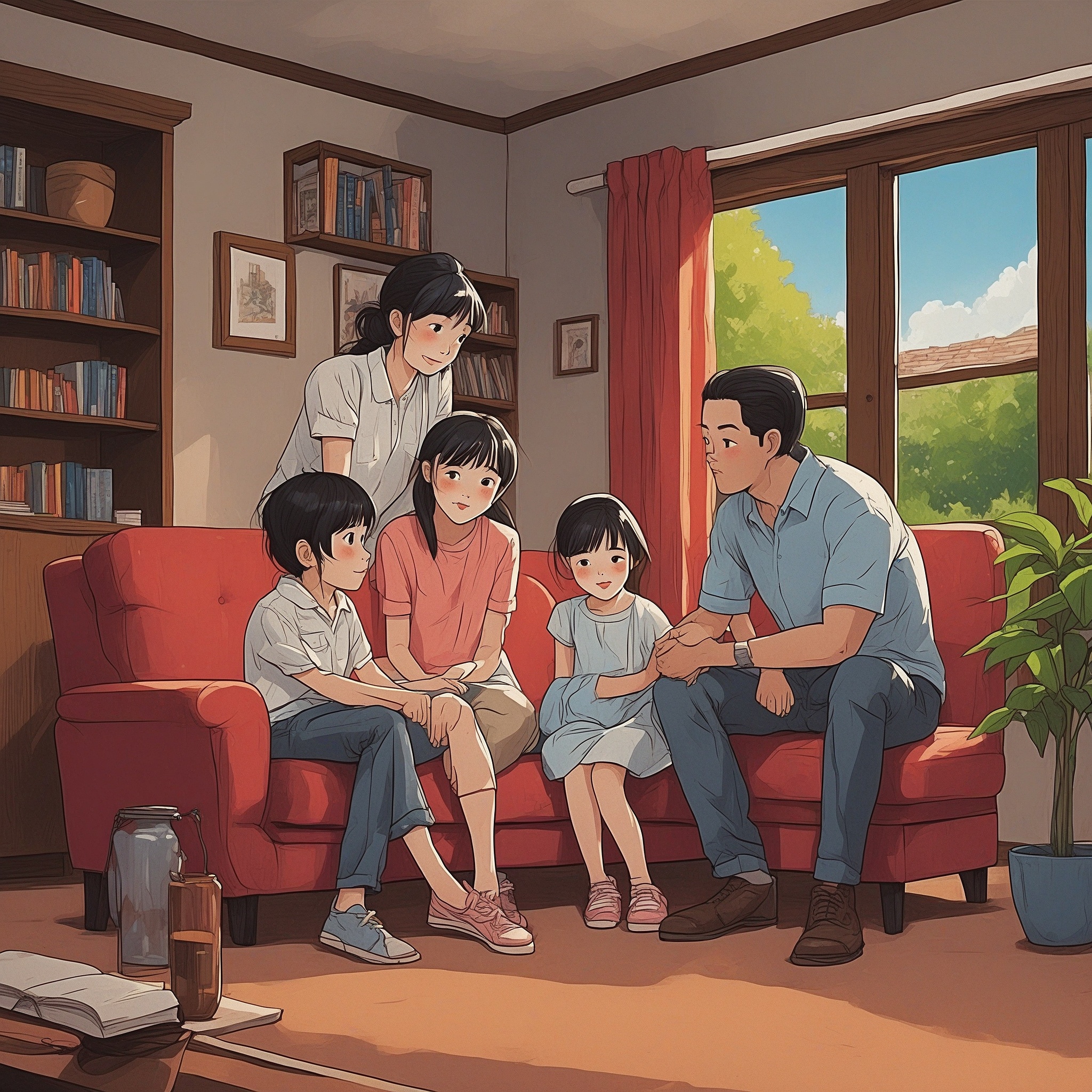なぜ相続トラブルは増えるのか?
相続トラブルは昔から存在しますが、近年では少子化や晩婚化、家族構成の多様化、資産構造の変化(不動産偏重など)から、家庭ごとの事情が複雑化し、トラブルの件数も増加傾向にあります。相続をめぐる争い、いわゆる「争族」は、遺言や遺産分割協議が不十分な場合、相続人同士の認識のズレや不満、遺留分侵害などが発端となることが多いです。
主な相続トラブルが起こる要因…
- 不動産が財産の大半を占めている
- 財産の全体像や詳細が相続人に共有されていない
- 家族構成(再婚、認知、内縁など)が複雑である
- 法定相続や遺留分の理解不足
- 遺言書の不備や不在
相続トラブルを回避するための準備
トラブルを未然に防ぐためのスタートは「見える化」と「合意形成」です。
- 財産の現状把握とリスト化
現預金・有価証券・不動産・生命保険など、相続の対象になる全ての資産と負債を一覧にしておきます。使い道がなく放置された不動産や共有名義の物件がトラブルの火種になりやすいので、現状をしっかり確認しましょう。 - 相続人の洗い出し
戸籍や家族関係図を確認し、法定相続人が誰なのか把握します。思わぬ相続人(例えば、前妻の子や認知した子ども)が判明することもあります。 - 家族間コミュニケーション
将来的な資産承継について家族・相続人と話し合い、「どんな資産がどれだけあるのか」「どのような意向があるのか」を共有しておくと、誤解や不信感を減らせます。 - エンディングノートの活用
生前に希望や想いを書き残しておくことで、家族内での意思疎通が円滑になり、相続時の争い予防に役立ちます。

絶対に押さえたい!遺言書の正しい作り方
遺言書は「自分の財産を誰にどのくらい残すか」を意思表示できる唯一の法的手段です。
作成には2つの方式があり、それぞれに特徴と注意点があります。
| 遺言書の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | いつでも作成でき費用がかからない | 紛失・偽造のリスク、要件不備で無効の可能性 |
| 公正証書遺言 | 法的に確実で安心 | 費用がかかる、公証人との手続きが必要 |
作成時のポイント
- 財産目録は具体的かつ詳細にまとめる
- 財産分割の理由や想いも伝えることで、相続人の納得度が高まる
- 遺留分も考慮した上で、バランスの取れた内容に
- 完成した遺言書は確実に相続人が分かる場所へ保管、公正証書遺言なら公証役場で原本保管も可

生前贈与や信託の活用で、争族を未然に防ぐ
「生前贈与」や「家族信託」は、資産を生前に分配したり管理したりする現代的なトラブル予防策として注目されています。
- 生前贈与
年間110万円までなら贈与税が非課税となる「暦年贈与」を活用し、家族ごとに合理的な資産分散が可能です。孫への教育資金一括贈与や住宅取得資金の贈与特例なども人気です。 - 家族信託(民事信託)
家族や信頼できる第三者に資産管理・運用・承継を託す制度。認知症などで自分で資産管理が困難になった場合にも、信託で指定した受託者が財産を動かせるため、柔軟かつ安全な承継が叶います。 - 生前贈与・信託時の注意点
税制や手続きが複雑な場合が多いため、必ず税理士や弁護士、信託会社など専門家の助言を受けましょう。

不動産相続が生む典型例
不動産は遺産総額の多くを占めるケースが多く、現金のように等分しにくいため相続争いに直結しやすい資産です。
不動産相続トラブルの代表例
- 遺産の大半が自宅や収益物件で、現金化が難しい
- 共有名義にしてしまい、利用や売却方針で揉める
- 相続税の納付資金が不足し、納税・不動産売却で混乱
主な解決策
- 不動産の分割代償金(他の相続人に現金で相当分を渡す)
- 生前に売却や利用方針を明確化
- 遺言で分割方針と理由を書き残す
- 専門家(司法書士、不動産会社、税理士)への相談

これからの資産承継:専門家と安心の未来設計
現代の資産承継は制度や税制もアップデートされ、プロのサポートが身近になっています。
トラブル回避のコツは「早めに・十分に・細やかに」です。
- 相続発生前から、税理士・司法書士・弁護士などに相談
- 資産や家族構成の体系的な“見える化”
- 最新の税制・補助金・各種制度の活用
- 万一トラブルに発展した場合の“冷静な協議と調整”
さらに、Webサービスや専門家ポータルを活用した最新情報取得も有効です。相続・承継において「分からないから放置」せず、“未来のトラブル防止=今やるべき具体策”を一つひとつ実践していきましょう。
現代の資産承継は「家族の絆を守り、次世代に安心を残す」ことに他なりません。